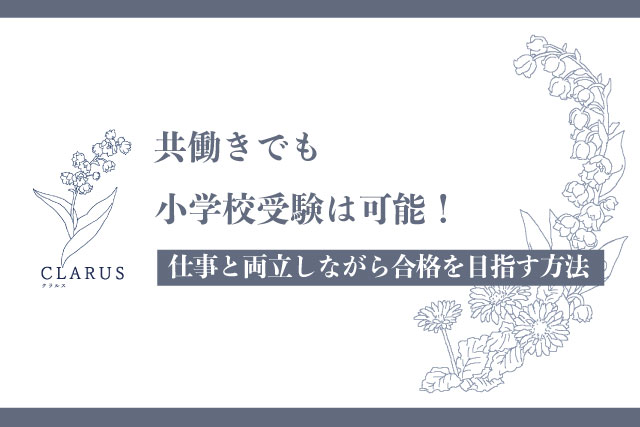「忙しい毎日の中で、子どものお教室通いや家庭学習をどのように管理すればよいのか」、「そもそもお教室の送迎が難しい」、「夜遅くまで勤務があり、子どもの受験勉強まで手が回らない」などの悩みは尽きません。
共働きの家庭で小学校受験を考える場合、仕事と受験準備をどう両立させるかが最大の課題ではないでしょうか。
しかし、実際には、共働き家庭でも小学校受験に成功しているケースは数多くあります。
- ポイントは、シッターサービスや家庭教師のサポートなど、時間と手間を省ける仕組みを上手に活用しながら、無理なく着実に学習を進めていくことです。
この記事では、共働き家庭が小学校受験を考える際に押さえておきたいポイントや、スケジュール管理の事例などを詳しく紹介していきます。
仕事と子どもの勉強を両立させたい、送迎など受験サポートも含んだ受験対策が必要といった場合に、ぜひ参考にしてみてください。
【結論】共働き家庭でも小学校受験は十分可能!

結論からいうと、共働き家庭でも小学校受験の合格を目指すことは、十分に実現可能です。
確かに、仕事との両立を考えると、受験準備のための時間や労力を確保するのは、大きな課題かもしれません。
しかし、近年は、家庭教師などでは、共働き家庭やワーキングマザー向けのサポートがみられるようになってます。
たとえば、家庭教師サービスの中には「送迎サービス」を提供している会社があります。
送迎付き家庭教師サービスは、保護者が働いている時間に、スタッフが保育園や習い事教室に子どもを迎えに行き、自宅やカフェでレッスンを行うというものです。
そのため、通園・通塾送迎の時間を削減できるだけでなく、保護者が働いている間に子どもをリアルタイムで任せられます。
保護者の仕事が忙しい場合でも、子どもの学習を進められるため、効率的な受験対策が可能です。
このような共働き家庭向けのサービスを上手に活用すれば、時間に制約があるケースでも、無理なく受験準備を続けられます。
共働き家庭で小学校受験を選ぶ家庭が増えている
共働き家庭の増加にともない、小学校受験を検討する家庭も年々増えています。
その背景には、「より早期に進路を固めて子どもの将来の負担を減らしたい」、「中学校受験のタイミングでは良い塾が空いていないかもしれない」といった思いがあります。
中学受験の準備は近年ますます早期化・激化しており、学習塾選びやスケジュール調整も難しくなってきています。
もし、小学校受験で早めに進路を決められれば、エスカレーター式で進学でき、中学受験やさらに先の準備に余裕ができ、結果として後々の負担が減ります。
また、お子さんの興味関心のあることに時間を費やせるのも利点です。
こうした背景により、小学校受験を選ぶ家庭が増えているのです。
一方で、小学校受験は親が主導となるため、子どもが自主的に勉強するわけではなかったり、塾や家庭教師の費用の負担も大きいことから、小学校受験を諦めてしまうケースも見受けられます。
しかし、実際には、早めに進路が決まれば中学校受験の費用はかかりません。つまり、長期的にはメリットの多い選択といえます。
進学先が私立小学校である場合、教育環境やカリキュラムを自由に選べることがあります。
こうした、子どもに合った学校の設備や指導方針のもとで授業を受けられる点に、魅力を感じる保護者も少なくありません。
また、公立小学校に対して不安がある場合でも、受験を通じて子どもの学力や適性をしっかり確認できることはメリット。
勉強の習慣がなかった子どもでも、受験勉強に触れたことで、進学後の学びとも向き合いやすくなるでしょう。
このように、社会的背景や教育事情が重なり、「共働き家庭でも小学校受験を選ぶ」という流れが強まっています。
早めに情報収集と準備を進め、家庭に合ったサポートを選ぶことで、仕事と受験を両立しながら子どもの可能性を広げられるのです。
共働きで小学校受験に成功するために抑えるべきポイント

共働き家庭が小学校受験を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 学習塾の選び方
- 受験する小学校の選び方
- スケジュール管理
以下からは、受験成功のポイントを順番に解説します。
学習塾の選び方
共働き家庭が学習塾を選ぶ際には、柔軟にスケジュールの調整ができるかどうかが重要です。
日中働いている共働き家庭にとっては、通塾のための送迎が難しく、負担が大きくなってしまうためです。
一方、家庭教師であれば、子どもの学習時間を柔軟に設定できるうえ、移動の手間も省けます。
家庭教師の中には、幼稚園、保育園や習い事先から送迎をしてくれるサービスを用意しているところもあるので、「お教室に通わせたいけど通わせられない」という問題も解消されやすいでしょう。
受験する小学校の選び方
共働き家庭が学校を選ぶときは、以下のポイントをチェックしておくとスムーズです。
- アフタースクール・預かり保育・給食体制が充実しているか
- 送迎バスがあるか・交通アクセスがよいか
- IT教育が進んでいるか
- 学校行事のスケジュール・保護者会・PTAの負荷はないか
- 働く保護者向けにサポート制度はあるか
- 小学校における「共働き家庭の割合」はどれくらいか
以下からは、受験する小学校の選び方をそれぞれ順番に見ていきましょう。
アフタースクール・預かり保育・給食体制が充実しているか
受験しようと思う小学校に、放課後に子どもを預かってくれるアフタースクールや、学童保育があるのか、内容はどのようなものかを事前に確認しましょう。
共働き家庭にとっては、子どもを安全に預けられる環境があるかどうかが重要です。
また、給食の体制が整っていれば、お弁当作りの負担を軽減できます。
とくに平日の朝はバタバタしやすいため、給食の有無は大きなポイントになるでしょう。
送迎バスがあるか・交通アクセスがよいか
小学校までの交通アクセスが良いかどうか、あるいは送迎バスが運行されているかは、共働き家庭にとって重要です。
通学に関わる負担を少しでも減らせるかどうかで、子どもの体力面や保護者の時間的な余裕ができるかどうかが、変わってくるでしょう。
IT教育が進んでいるか
最近は、小学校の段階からタブレット端末を使ったオンライン授業や宿題の提出が行われることも増えてきました。
IT化が教育の現場に進んでいる学校であれば、連絡もデジタル化されることも一般化し、仕事中でもスマホで連絡事項を受け取りやすくなります。
また、提出書類をアプリで送付できるなど事務手続きも効率化されます。
このように、ただでさえ時間に余裕がなく、できるだけ学校とのやり取りを簡略化したい共働き家庭なら、ITを活用した仕組みが受験したい小学校にあるかどうかも確認しておくとよいでしょう。
学校行事のスケジュール・保護者会・PTAの負荷はないか
運動会や参観日などの学校行事が平日だけに集中していないか、保護者会の頻度が極端に多くないか、空けづらい時間帯ばかりではないかなど、事前にチェックしましょう。
せっかく両親が共働きのまま私立の小学校に入れても、働く保護者向けの工夫が少ないと、入学後に仕事をセーブしなくてはいけなくなってしまうからです。
また、PTA活動は必須ではないということを理解しておくのも大事なポイントです。
仕事との兼ね合いでどうしても参加が難しい場合は、学校側に相談する、あるいは負担が少ない役割を担うなどを申し出ましょう。
働く保護者向けにサポート制度はあるか
学校によっては、在宅勤務を行う保護者向けに独自のサポート制度を用意してている場合があります。
たとえば、オンラインでの個人面談、数日間にわたる授業参観日の用意、一部授業のライブ配信などです。
このように、入学した後でも仕事を続けられるようなサポートがあるかを確認しておくと、共働き家庭でも安心です。
小学校における「共働き家庭の割合」はどれくらいか
実際に学校見学や説明会などで、「働く保護者は何割ぐらいか」や「保護者参加イベントの時間帯はどうなっているか」を確認すると良いでしょう。
具体的には、「どのくらいの保護者が共働きなのか」、「保護者参加のイベントは平日の昼間が中心だったりしないか」、「土日を活用しているのか」などを確認しておくことで、入学後のイメージを具体的につかみやすくなります。
こういった点を確認すると、入学後のリアルなイメージが想像できます。
スケジュール管理
時間がない共働き家庭が小学校受験を成功させるには、次のようなスケジュール管理の工夫がポイントです。
- 「平日は母親、週末は父親が担当」など分担を明確にする
- 忙しくても工夫して学習時間を確保する
- ルーティン化や外部の力を取り入れる
以下から、順番に解説していきます。
「平日は母親、週末は父親が担当」など分担を明確にする
家族内での役割分担をきちんと決め、学習以外の家事や用事もリスト化しておくと、保護者の負担を分散できます。
また、受験期の1年間だけは小学校受験を最優先にして、掃除や料理は「ほどほどのクオリティでOK」と割り切るなど、妥協点をつくることも大切です。
夫婦だけで手が回らない場合は、親戚に協力をお願いしたり、家事代行サービスなどを検討しましょう。
家事を他人に任せるのは抵抗があるという方でも、子どもの送迎だけに限定して依頼するなど、部分的なサポートを活用すれば、負担を大幅に減らせます。
忙しくても工夫して学習時間を確保する
ここでは、忙しい中でも工夫して学習時間を作り出す方法を解説します。
学習時間確保の考え方として、以下が挙げられます。
- 朝学習の活用(出勤前の短時間を活用)
- 夜学習の効率化(限られた時間で成果を出す)
- 休日を使った集中学習
以下からは、それぞれのポイントを解説していきますので、取り入れやすい方法から試してみてください。
朝学習の活用(出勤前の時間を活用)
朝の隙間時間でも勉強することはできます。
睡眠をとった後には疲労が軽減されており、効率よく学習できるのです。
具体的には、朝の時間を使って単元別の問題をこなされるのがおすすめ。
また、朝は準備で忙しく、子どもの勉強に付き合うのが難しい際には、動画での学習を取り入れると、親は朝の準備をしつつも、子どもは勉強する、といった環境がつくれます。
夜学習の効率化(限られた時間で成果を出す)
平日の夜は子どもも親も疲れが溜まりやすいので、長時間の学習ではなく、少ない時間でもよいので集中して勉強をしましょう。
「夕飯の順番をしている間に巧緻性をする」、「勉強道具はすぐ手に取れる状態にしておく」といった工夫を習慣づけることで、短時間でも「慣れ」の力により集中力を発揮しやすくなります。
休日を使った集中学習
休日はまとまった時間をとりやすいので、苦手単元やお教室の復習などを行うのに最適です。
一方で、子どもが長時間集中するのは難しいため、何クールかに分けて勉強し、合間には博物館や科学館での学び体験を取り入れて知識を深める機会も大切にするとよいでしょう。
このように、遊びと勉強のバランスを保ち、子どものモチベーションを保って勉強を続けると結果に繋がりやすいです。
ルーティン化や外部の力を取り入れる
スケジュール管理をする際に、毎週の予定をあらかじめ決めてしまい、ルーティン化するのも効果的です。
たとえば、「頑張った後に好きな動画を見せる」、「今日は思い切って外食にする」、「掃除は翌日に回す」などの小さなご褒美や妥協点を用意して、親子双方のストレスを軽減しましょう。
それでも難しい場合は、祖父母に送迎を手伝ってもらったり、シッターサービスを利用したり、「送迎付きの小学校受験専門家庭教師」を利用したりして、サポート体制を整えることが大切です。
夫婦の役割分担がうまくいかないときも、外部サービスを活用すればうまく乗り越えやすくなるでしょう。
共働き家庭の小学校受験スケジュールの組み方事例

ここでは、次のように小学校受験のためのスケジュールの組み方をいくつか紹介します。
- 事例①:朝型学習+土日特訓
- 事例②:家庭教師やお教室&祖父母サポートを活用
- 事例③:効率重視で受験準備を最小限に
これから紹介する事例の中で、自分たちの生活スタイルに合った方法があれば、ぜひ取り入れてみてください。
以下から、詳しく見ていきましょう。
事例①:朝型学習+土日特訓
朝型の生活習慣の家庭では、平日の朝の時間で単元学習をし、土日は苦手単元やお教室の復習に取り組むというやり方があります。
子どもが夜に疲れている場合には、朝のほうが頭が冴えていることも多いです。
記憶、知識、言語、運筆を行いつつ数の操作などの基礎的な勉強を朝型で行います。
土日は、お教室の復習をしつつ、苦手な領域単元の再確認にあてる時間も確保。
さらに、公園や博物館などへのお出かけを「学びの延長」と捉え、好奇心を育てる取り組みを取り入れることもできます。
事例②:家庭教師やお教室&祖父母サポート(シッターサービス)を活用
共働き家庭にとって、送迎やスケジュール調整が難しい場合は、家庭教師やお教室を積極的に活用するのがおすすめです。
通塾はシッターサービスを利用され学習面は家庭教師を利用することで子どもの進度に合わせてカリキュラムを組んでくれるため、無駄がありません。
実際に、家庭教師サービスとシッターサポートを活用して、小学校受験に成功した家庭の事例をご紹介します。
思い返せば、我が家は年中の12月からのスタートとなり、決して早いスタートではありませんでした。
幼児教室へは年中から通い始めていたものの、両親共働きということもあり日々のスケジュールをこなすことに精一杯で自宅学習もままならない状態でした。そこで、焦った結果、送迎付きという文言に惹かれご連絡させていただいたのがクラルスでした。早生まれということもあってか、マイペースを貫く娘に先生方はとにかく柔軟に対応くださり、保護者の悩みにも真摯に向き合ってくださるその存在は、まるで家族のようで、試験のたびにその強い後ろ盾があることで安心して受験へ臨むことができました。
家庭教師での時間はペーパーのみならず集中力が切れやすい娘のために、合間に折り紙や縄跳び、鉄棒などプリント以外の指導もしていただきました。 幼児教室での模試では下から数えたほうが早かった順位が、着実に上がっていき、受験直前ともなると早生まれにも関わらず1桁の順位を取れるようになりました。引用元:CLARUS「合格実績」
さらに、祖父母が近くに住んでいる場合は、送迎や学習フォローなどをお願いすると、親の負担がぐっと軽くなるでしょう。
祖父母などに頼れない場合でも、サポートが受けられる家庭教師やシッターを選べば、子どもの学習だけでなく、生活習慣まで手厚くフォローしやすくなります。
事例③:効率重視で受験準備を最小限に
平日・休日を問わず「短時間・集中型」の方法で、必要最低限の勉強に絞り込むやりかたもあります。
過去問や模試を徹底的に活用すれば、「合格点を取るのに必要な分野」に集中して学習することで、負担を最小限に抑えられます。
また、土日には自然観察や文化施設へのおでかけなど、家族で楽しく過ごす時間を取り入れることで、子どもの好奇心やストレス解消にも配慮。
結果として、短時間でも効率的に実力をつけられるうえに、家族の雰囲気も良好なまま小学校受験を乗り越えやすくなるのです。
共働き家庭の小学校受験でいちばん大切なことは「完璧を目指さない」
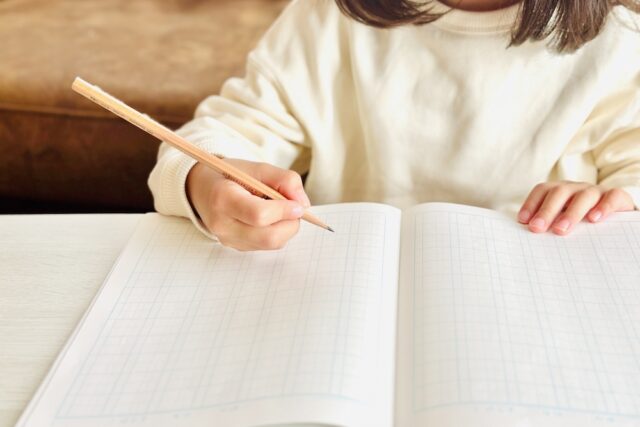
共働き家庭が小学校受験に取り組む際、ついやってしまいがちなのが何もかも完璧にしようとすることです。
しかし、仕事や家庭のことを考えながら、受験対策まですべて完璧にこなすのは至難の業。
結果的に家族全員が疲弊し、子どもも親もストレスを溜めてしまうケースも珍しくありません。
小学校受験は、あくまでも「子どもの将来の選択肢を広げる手段」です。
家庭内がギクシャクしてまで受験に成功しても、それでは本末転倒ではないでしょうか。
家族や祖父母との関係を壊してまで頑張る必要はありませんし、家事や育児をすべて完璧にするのも現実的ではありません。
むしろ、「受験期の1年間は家の掃除を最低限にする」、「時にはデリバリーや外食で済ませる」など、思い切って力を抜くポイントを作るほうが、長い目で見れば家族の負担が軽減され、結果として子どもの学習効率も上がるでしょう。
また、夫婦や祖父母とのコミュニケーションも大切です。
「今、どれくらい忙しいのか」、「どの作業を誰が担当するか」といった情報を共有し、協力して受験準備を進めることで、家庭内の空気がギスギスしにくくなります。
完璧主義にならずに、やるべきところはしっかり押さえつつ、難しい部分は外部のサポートを上手に利用しましょう。
こうした柔軟な姿勢が、共働き家庭の小学校受験を成功させるカギになります。
共働きでも小学校受験は可能!
この記事では、共働き家庭の小学校受験対策についてお伝えしました。
共働きでも小学校受験を成功させる家族はたくさんいますし、学校側のサポート体制や家庭のスケジュール管理、夫婦の役割分担がうまくいけば、スムーズに合格に近づけます。
また、勉強自体を外部に丸投げしたいのなら、家庭教師を利用するのがおすすめです。
家庭教師なら柔軟性が高く、その道のプロが自宅での学習をサポートしてくれるため、忙しい保護者でも安心して任せやすいでしょう。
共働き家庭の小学校受験は、しっかりしたサポート体制と効率的な学習計画があれば、十分に乗り越えられます。
今回ご紹介したポイントを参考に、ぜひ前向きに小学校受験に取り組んでみてください。
クラルスは共働き家庭に寄り添った小学校受験のサポートをします
クラルスでは、下記のような強みを活かし、忙しい共働き家庭をお手伝いします。
- 送迎サービス:保育園や習い事先お迎えを代行し、そのまま自宅やカフェでレッスンを実施
- 難関校対策:経験豊富な講師陣が、志望校の出題傾向に合わせたカリキュラムを提供
- 柔軟なスケジュールと対応:家庭のライフスタイルに合わせてレッスン時間や曜日を調整、面談ができない日はメールでの報告や対応
こうしたサービスを活用することで、共働きであっても子どもの受験準備を効率よく進められます。
さらにクラルスでは、お忙しい方に向けた体験レッスンもご用意しております。
詳しくはクラルス公式サイトをご覧いただき、ぜひお気軽にお問い合わせください。
「子どもの学力を伸ばしながら、安全に預けたい」、「仕事が忙しくても小学校受験を成功させたい」という保護者の方に寄り添い、全力でバックアップさせていただきます。