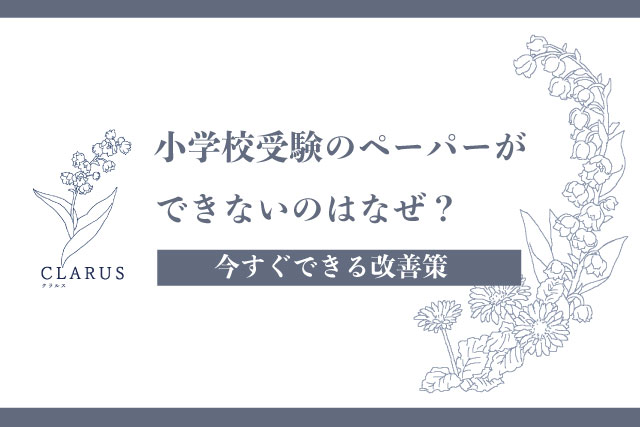小学校受験のペーパーが思うようにできないと「うちの子、大丈夫かな?」と不安になりますよね。特に周囲の子がスラスラ解いているのを見聞きすると、つい気持ちが焦ってしまうものです。
しかし、実は「ペーパーができない=勉強に向いていない」というわけではありません。
お子様の発達段階や学習方法の影響で、まだ力が十分に伸びていないだけのことが多いのです。
この記事では、なぜペーパーができないのか、どうすれば力をつけられるのかをわかりやすく解説します。
「自分の子どもだけが、ペーパーができないのだろうか」と不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。
小学校受験でペーパーができないのは当然!理由は、子どもまだ発達中だから
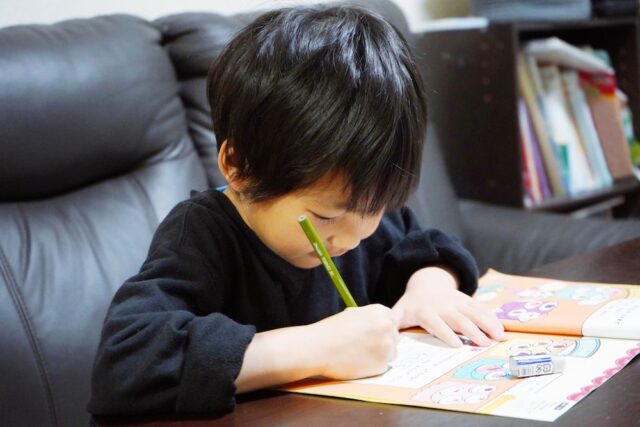
小学校受験で「ペーパーがうまくできない」と悩む方は多いですが、実はごく自然なことです。
なぜなら、5歳〜6歳の子どもの脳や認知機能は十分に発達しきっていないからです。
お子様が「できない」と感じるのは、その年齢では当たり前のこと。
決してお子様や家族のせいではありません。
ペーパーができないのは当然だといえる理由は、以下の通りです。
- 小学校受験の対象年齢では、紙のテストが難しいから
- 5~6歳の子どもが紙のテストをスラスラ解けるほうが不自然だから
- 受験期の脳の発達は、ペーパー試験に向いていないから
ここからは、理由を1つずつ解説していきます。
小学校受験の対象年齢では、紙のテストが難しいから
小学校受験は、5〜6歳の子どもを対象としています。
しかし、この年齢ではまだ読み書きの力や読解力が十分に発達していないことから、ペーパーとの相性はよくありません。
たとえるなら、楽器を習い始めたばかりの初心者に難しい楽譜を渡して、すぐ演奏するように促すようなものです。
子どもに無理をさせすぎると、勉強そのものが嫌いになる可能性もあります。
まずは親が「この年齢ならペーパーは難しくて当然」と理解し、気持ちに余裕を持つことが大切です。
5~6歳の子どもが紙のテストをスラスラ解けるほうが不自然だから
ペーパーを解くには「文字を読む」「内容を理解する」「答えを書く」など、複数の作業を同時にこなす力が必要です。
これは幼児にとって簡単なことではなく、スラスラ解けるほうがむしろ珍しいのです。
しかしながら、「うちの子はペーパーができないのかも」と心配のあまり、勉強させるときにペーパー問題の枚数を増やしすぎると、子どもにとってがストレスが高まってしまいかねません。
周囲の、ペーパーができる子と比べて焦ったり落ち込んだりする時もあるかもしれませんが、伸びるタイミングはどの子どもも同じなわけではありません。
今の点数にとらわれず、できていることをほめることで学ぶ意欲を引き出してあげましょう。
受験期の脳の発達は、ペーパー試験に向いていないから
スイスの心理学者ジャン・ピアジェは、子どもの認知発達を4段階に分け、そのうち2〜7歳の時期を「前操作期」と定義しました。
この時期の子どもは、目に見えるものや実際に体験したことを中心に物事を理解します。
一方で、想像力がまだ十分に発達していない時期でもあるため、ペーパーのような抽象的な問題には苦手意識を持ちやすいのです。
特に、小学校受験でよく出題される「図形」や「数量」の問題は、7〜11歳ごろに発達する「具体的操作期」の能力が関係しています。
つまり、ペーパーというテストを受けさせられている時点で、年齢以上の能力を求められているため、苦手に感じても無理はないでしょう。
さらに、5〜6歳の子どもは視覚情報よりも触覚情報のほうが記憶に残りやすいともされています。
つまり、実際に手を動かして学ぶほうが効果的であり、紙の上の情報だけではイメージしにくいのです。
このように、ペーパーがうまくできないのは子どもの発達段階を考えれば当然のこと。
親は、お子様の成長に合わせた無理のないサポートを心がけることが大切です。
小学校受験で「ペーパーができない」=「能力が低い」わけではない!
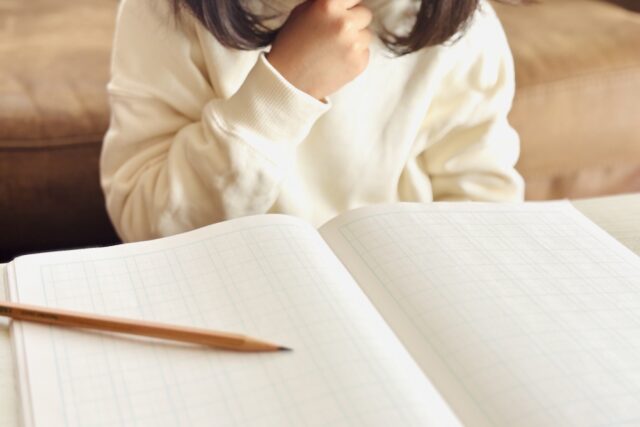
ペーパーができないのは、決してお子様の能力が低いからではありません。
多くの場合は「まだ慣れていない」「解き方のパターンを身につけていない」という理由で苦戦しているだけです。
また、ペーパーができる子が必ずしも問題を深く理解しているとはかぎりません。
単に、数をこなしてパターンを暗記しているだけかもしれないのです。
周囲の子と比較するのではなく、お子様の成長に目を向けながらサポートしていきましょう。
まずは「ペーパーができない」の正体を見極めることが大切
「ペーパーができない」と一言でいっても、つまずきの原因は人によってさまざまです。
お子様がどこでつまづいているのか、よく観察してみましょう。
具体的には、次のようなポイントでつまづいている可能性があります。
- 語彙力・読解力が不足している
- 思考整理・解き方がわからない
- 時間内に解けない
- ちょっとしたミスが多い
- できているのにできないと親が思いこんでいる
以下からは、ペーパーにおけるつまづきの理由について、それぞれ詳しく解説します。
語彙力・読解力の不足
文章の意味がよくわからなくて、問題を解く前に戸惑ってしまうことがあります。
たとえば、「次の中で、仲間はずれはどれですか?」という問題を出されたとき、「仲間はずれ」という言葉自体の意味がわからず、何を答えればいいのか迷ってしまうことがあるのです。
また、「くま君に〇をつけて、りんごに△をつけなさい」といった指示が複数ある問題では、最初のほうの指示を読んだあと、後半の指示を忘れてしまうこともあります。
思考整理・解き方がわからない
問題を解くときに、何をどう考えればいいのかわからず、手が止まってしまうことがあります。
たとえば、「ぶどうの重さとバナナの重さを同じにするには、バナナは何個必要でしょう?」というような問題では、「ぶどうとバナナをどうやって比べればいいの?」と混乱してしまうことがあるのです。
また、図形の問題で、立体の展開図を見せられても、実際にどんな形になるのか想像しにくく、なかなか答えが出せないこともあります。
時間内に解けない
問題の意味を理解するのに時間がかかってしまい、考え始めたころにはすでに終了のチャイムが鳴ってしまうことがあります。
また、丁寧に答えを書こうとするあまり、他の問題に進むのが遅くなり、最後まで解ききれないこともあります。
ちょっとしたミスが多い
計算そのものは正しくできているのに、答えを書く場所を間違えてしまったり、問題を最後まで読まずに早とちりして、求められている答えと違うことを書いてしまったりすることがあります。
「あっていたのに、もったいない」と思うようなミスが何度も続くと、悔しい気持ちになることもあるでしょう。
できているのにできないと親が思い込んでいる
以前は問題の意味がよくわからず、ただなんとなく答えていたのに、最近は問題文をじっくり読むようになっている、といったことが実は起きていることがあります。
点数にはまだ反映されていなくても、少しずつ理解できるようになっている証拠です。
また、惜しいミスが増えているのも、「まったくわからない」状態から「あと少しで正解できる」レベルに成長している証拠かもしれません。
小学校受験で「ペーパーができる子」には共通点がある!
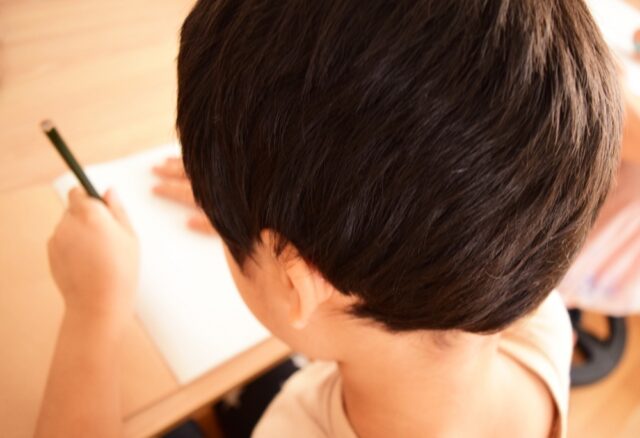
小学校受験でペーパーができる子には、いくつかの共通点があります。
実は、最初からペーパーが得意だったわけではなく、特定の習慣や環境が整っていることが多いのです。
まず、問題のパターンを把握していることが挙げられます。
同じような問題を何度も解くことで、「これは前にやったものと似ている」と気づけるようになります。
新しい問題に直面しても、過去の経験と結びつけて考えられるのです。
次に、自分で考える習慣が身についていることも大切です。
答えをすぐに教えてもらうのではなく、自分で考える時間を持つことで、じっくりと問題に向き合う力が養われます。
また、「どうしてそう思ったの?」と質問されることで、理由を考える習慣がつき、思考力が伸びていきます。
さらに、間違えても落ち込まず、試行錯誤を楽しめることも特徴です。
たとえば、親が「間違いは学びのチャンスだね」というように声をかけることで、失敗を前向きにとらえられるようになります。
また、親自身が挑戦する姿や失敗から学ぶ姿を見せることも、子どもにとって良い影響となります。
さらに、「今日は〇問も正解したね!」と具体的にほめられることで、自信を持って取り組めるようになるのです。
図や具体物を使って考えることに慣れていることも重要です。
問題を解くときに「絵を描いてみようか」と促されることで、視覚的に整理しながら考えられます。
また、ブロックやおはじき、折り紙などを使って手を動かしながら学ぶことで、理解が深まりやすくなります。
折り紙を使って形を作ることで、図形の感覚も自然と身についていくでしょう。
小学校受験でペーパーができない時の具体的な対策方法
ペーパーが「なかなかうまくできない」と感じる場合、対策が必要です。す。
具体的なペーパー対策は、次の2つにわけられます。
- 勉強のやり方
- 親の関わり方
以下からは、それぞれのポイントについて、順番に解説していきます。
勉強のやり方

ご家庭でのペーパー対策は、効果的な勉強方法を取り入れることが大切です。
効果的な勉強のやり方は、以下の通りです。
- 語彙力・読解力を強化する
- ミスを減らすために、指示を正しく理解させる
- ノルマは「枚数」ではなく「時間」で決め、反復練習させる
- 簡単な問題と難しい問題をバランスよく組み合わせる
- ペーパーだけでなく、実体験を通して学ばせる
- ペーパー対策できる家庭教師を取り入れる
次から、1つずつ解説していきます。
語彙力・読解力を強化する
語彙力・読解力は、ペーパーだけでなく指示行動試験など他の試験でも必要になります。
一朝一夕には身につかないので、日常生活の中で楽しく取り入れましょう。
すぐにでもできることとして、たとえば以下があります。
- 買い物リストを一緒に作る(「にんじん3本、玉ねぎ2個…」と単位を意識させる)
- 同じ意味の言葉は?反対の意味の言葉は?という言葉遊びをする
- 読み聞かせの後に「どんな話だったかな?」と要約してもらう
ミスを減らすために、指示を正しく理解させる
「問題の読み間違い」「指示の聞き間違い」によるミスは、以下のようなちょっとした工夫で減らすことができます。
- 問題文を指でなぞりながら読む(目で追うだけでなく、指を使うことで読み間違いを防ぐ)
- 「~以外」「~より多い」など、言葉のニュアンスが複雑な言葉は一緒に確認する
- 問題文を自分の言葉で言いかえてもらう(理解の確認のため)
ノルマは「枚数」ではなく「時間」で決め、反復練習させる
ペーパー学習のノルマを「枚数」ではなく「時間」で決めると、モチベーションが維持しやすくなります。
すぐにでもできることとして、以下が挙げられます。
- 子どもに合った学習時間を設定する(例:「30分だけ集中しよう」)
- 簡単な問題から始めて、徐々に慣れる
- 「この問題は何分でできるかな?」と自分で予測してから解いてもらう
簡単な問題と難しい問題をバランスよく組み合わせる
簡単な問題と難しい問題をバランスよく組み合わせることで、自信とチャレンジ精神の両方を育てられます。
すぐにでも 【明日からできることとして、以下が挙げられます。
- ペーパーの順番を「簡単な問題→難しい問題→簡単な問題」にする(楽しく始めて楽しく終わる)
- 簡単な問題も繰り返し解いて、スピードと正確さを上げる
ペーパーだけでなく、実体験を通して学ばせる
ペーパーの内容は日常生活の経験と結びついていることが多いため、実体験を通じて学ぶことで理解が深まります。
すぐにでも 【明日からできることとして、以下が挙げられます。
- 積み木や折り紙で遊んで、図形感覚を養う
- 買い物で「100円玉が3枚でいくら?」「おつりはいくら?」と計算することで数量の感覚を身につける
- 公園で植物や昆虫を観察することで、季節・常識の知識を身につける
- 親子で簡単な料理をしながら「次に何をするのか?」と手順を想像させるようにする
ペーパー対策できる家庭教師を取り入れる
家庭学習だけでは行き詰まりを感じたら、家庭教師やオンライン学習塾など専門的なサポートの利用も視野に入れてみてください。
ただし、個別指導である分コストは高額になりがちなので、予算と相談しながら検討しましょう。
親の関わり方

お子様の家庭学習に、親御様はどう関わればよいのでしょうか。
結論は、「学習意欲を引き出すこと」です。
次のポイントを意識すると、お子様の学習意欲を引き出しやすくなります。
- 「まだできないだけ」と前向きな声かけをする
- 親が焦ると、子どももプレッシャーを感じてしまうため気をつける
- 「受験のため」ではなく「学ぶ楽しさ」を伝える
- 子どもに合った学習方法を探す
以下からは、それぞれのポイントについて解説していきます。
「まだできないだけ」と前向きな声かけをする
「まだできないだけ」という視点を親が持つことで、子どもの成長を信じている、という姿勢を本人に示すことができます。
ただし、過剰に期待している、いつか絶対にできるようになる、というような雰囲気を見せてしまうと、子どもにとってストレスになってしまうので気をつけましょう。
「少しずつできるようになっているね」「この問題は前より早く解けたね」「難しい問題に挑戦してかっこいい!」というように、成長に目を向けた声かけをすると、子どもも自信を持って学習に取り組めるようになります。
親が焦ると、子どももプレッシャーを感じてしまうため気をつける
親が焦ると、子どもも不安になります。
「〇〇ちゃんはもっとできているのに」と他の子と比べたり「どうしてこんな簡単な問題が解けないの?」と叱ったりすると、子どもはプレッシャーを感じて学習意欲が低下してしまいます。
子どもを尊重し「あなたはあなたのペースで成長しているよ」と、安心感を与えることが大切です。
「受験のため」ではなく「学ぶ楽しさ」を伝える
勉強が「受験のためだけの勉強」になってしまうと子どもは学ぶことが苦痛になり、そこから伸びるのが難しくなります。
目の前の受験はもちろん大切ですが、学習は生涯にわたって続くもの。
「勉強は楽しいもの」と伝え、親子で楽しみながらさまざまな経験を積みましょう。
子どもに合った学習方法を探す
すべての子どもが同じ方法で伸びるわけではありません。
お子様の特性に合った方法を見つけましょう。
たとえば、厳しい指導で伸びる子もいれば、ほめる指導で伸びる子もいます。
また、学習環境についても、集団と個別の好みの違いもあるはず。
つまり、必ずしも有名だったり、ブランド色が強い塾が最適とは限らないため、お子様に合う方法を見極めましょう。
子どもに合った勉強方法を探すなら家庭教師がおすすめ!

小学校受験では、子どものタイプに合った学習方法を見つけることが成功のカギです。
特に、次のような子には、家庭教師の個別指導が向いているかもしれません。
- 集団塾では集中しづらい子:周囲の様子が気になって集中できない、マイペースで学びたい子には、マンツーマン指導が効果的。
- 実践的な学びが合う子:体験から学ぶタイプの子には、物を使った学習なども可能な家庭教師が適しています。
- 親の指導では反発してしまう子:第三者からの指導のほうが素直に受け入れられる子もいます。親子関係を良好に保ちやすいこともメリット。
家庭教師は、「苦手分野の克服に集中して、最短距離で力を伸ばしたい」「自宅ではやさしい問題で自信をつけさせたいから家庭教師に難しい問題を教えてもらいたい」など、一人ひとりに合わせた指導を受けられるのが魅力です。
ついていけない不安を感じずに、自信を持って学習を進められます。
また、以下のように、受験対策の面から見ても家庭教師は効果的です。
- 志望校の過去問対策を個別に実施できる(一斉授業ではないため、子どもの理解度に合わせられる)
- ペーパー・行動観察・面接など、必要な分野だけオーダーメイドで対策できる
- スケジュールに融通が利きやすい(共働き家庭でも無理なく利用できる)
- 送迎付きのサービスを利用すれば、親の負担を軽減できる
「うちの子に合う学習法がわからない」「塾が合わなかった」と悩んでいる方は、一度体験レッスンで家庭教師の指導を試してみることをおすすめします。
「クラルス」の家庭教師では、お子様の特性を見極め、一人ひとりに合った学習プランを提案しています。
初回体験レッスン(5,000円)も実施中なので、不安を感じている方は一度お試しください。
小学校受験でペーパーができないことは気にしなくてOK!親は焦りを見せないようにしよう
今回は、小学校受験でペーパーができない理由と、その対策について詳しく解説しました。
5~6歳の子どもにとって、ペーパー試験が難しいのは当然のことです。
まだ発達の途中であり、文字を読んだり、情報を整理したりする力が十分に備わっていないため、「できない」と感じるのは自然なことなのです。
大切なのは、焦らず、心配しすぎずにお子さんの成長を見守ること。
子どもは一人ひとり発達のペースが異なるもの。
今できないことも、適切な学習を続けていればできるようになります。
大切なのは、お子様の成長を見守りながら「どうすれば学びやすいか?」を工夫することです。
たとえば、実際に遊んだ経験から思考力を育てたり、個別指導を活用して苦手分野を克服したりすることで、自然に力がついていきます。
小学校受験はゴールではなく、お子様の未来につながる一つのステップです。
受験だけにとらわれず、これからの人生に役立つ力を育てるという視点を持ちましょう。
「ペーパーができない」と悩むよりも、お子様の成長を信じて温かくサポートしていくことが、結果的に最も効果的な対策になるはずです。